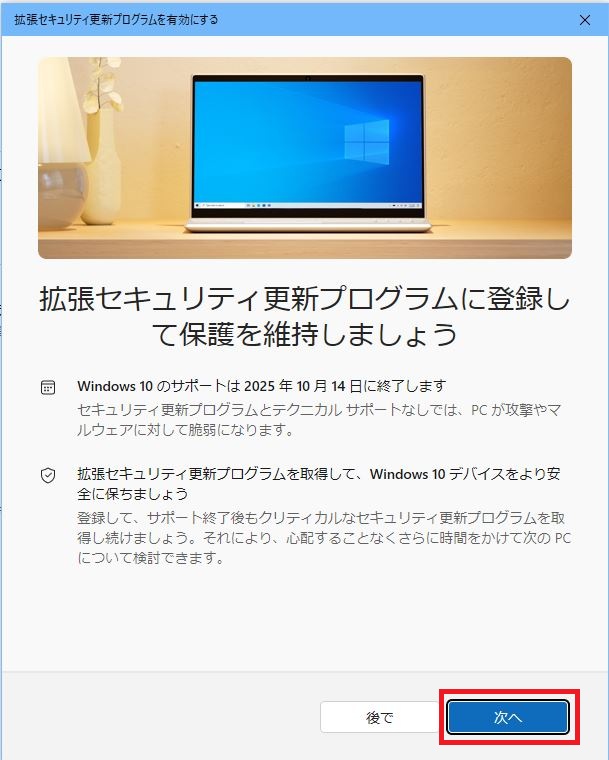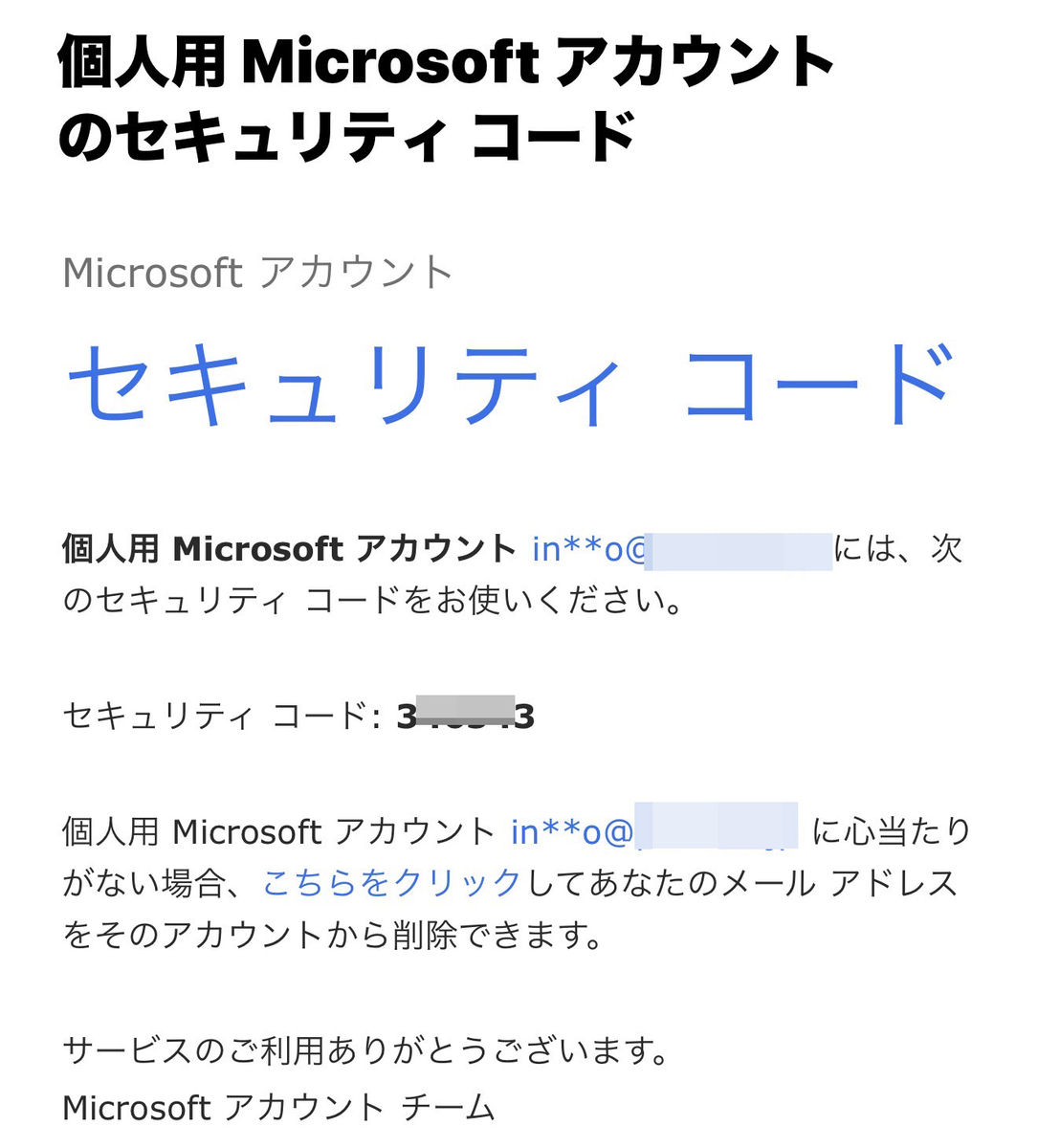起源はマラトンからアテナイ(現在のアテネ)まで勝利を知らせる為に兵士が走ったという故事が由来だとされています。諸説はありますがこの伝承をもとに近代五輪第1回目のアテネ大会では同じくマラトンからアテネの陸上競技場までの約40キロ(実測では37キロとも)で開催され現在まで途切れることなく実施されている競技の1つです。
42.195km?
諸説ありますが第1回以降、第2回と3回は約40キロ(1906年の10周年記念大会は約42キロ)で開催されていましたが第4回のロンドンでコースを設計したら26マイル385ヤード=42195メートルとなったとのことのようです。
といって以降の第5回は約40キロ、7回は約43キロでしたが大会後の1921年に国際陸連がロンドン大会の距離に統一することにし以降は現行の距離になりました。
※第6回は第1次大戦の為中止
88年を経て
オリンピックにおけるマラソン競技への女性参加は今回題材にしている1984年ロサンゼルス大会が1回目です。女性の長距離種目としては初の実施でした。
ちなみに第1回のアテネでの逸話として男子マラソンの翌日に同コースを完走した女性がいたとのことです(大会前に試走し完走した女性もいるとか)
さて本題に
1970年ころまでの日本のマラソン界は世界記録を更新したり、国際大会などでも上位の成績を収めていたので人気のスポーツでした。1970年代後半から90年代にかけても当時の世界歴代10傑に名を連ねる選手が複数いるマラソン強国でした。
悲願の出場
1984年ロサンゼルス大会の男子マラソン代表は旭化成所属の双子ランナーで有名な宗茂・宋猛さん、エスビー食品所属、そして日本のエースとされていた瀬古利彦さん。
3氏は共に不参加だった1980年のモスクワ大会に続き連続での代表選出でした。
中学生時は甲子園を目指し野球部に所属されながら体力づくりの一環で走るトレーニングは毎日欠かさなかったそうです。
あるとき陸上部からの誘いで大会に出たところ県記録をたたき出すほどに。
3年時に肩を故障され野球の道は断念されますが高校は県の陸上強豪校へ進まれます。中距離で大活躍され毎年12月に行われる高校駅伝でも3年連続で花の1区を走られます。
大学進学、日本のエースへ
現代でもそうですが、高校駅伝の有力選手の殆んどが関東の大学へ進学されます。
瀬古さんも同様に複数の大学からオファーがありましたが、早稲田大学を受験されます(当時スポーツでの推薦入学は無かったそうです)
結果は残念ながら不合格で1年海外留学ののちに翌年合格され競走部に入部。
以降は中距離からマラソンへ転向されモスクワ五輪を目指すことに。
最初に出場したのは1年生の2月。10位でしたが新人賞を獲得されます。
2年生時の12月に福岡国際マラソンで日本人最上位の5位に。
3年生時の12月に上記大会において当時の世界歴代10位、日本学生記録で優勝。
4年生時の4月にボストンマラソンで当時の世界歴代9位、日本学生記録更新で2位。
同12月にモスクワ大会選考を兼ねた福岡で日本人初の2連覇(宋茂さん2位、宋猛さんが4位)と驚異的な強さでした。
毎年1月に行われる箱根駅伝でも1年時から4年時までエース区間と呼ばれた「花の2区」を担当されます。なお3年時と4年時には新記録で区間賞を獲得される無双っぷりを発揮されていました。
不参加
オリンピックでも十分にメダルを狙えるとされていましたが、先述のとおり社会情勢で日本はモスクワ不参加を決定します。
当時アメリカのマラソン界でも強豪選手の1人が瀬古さんの初マラソンから4大会連続で同走しており1位・1位・6位・1位の成績を収めていたのがビル・ロジャースさん。
76年のモントリオール大会へは日本でも有名なフランク・ショーターさんとともに出場(国内予選は2位、本大会は40位)
瀬古さんが2位になったボストンマラソンでの優勝タイム2時間9分27秒は自己記録とともにエリア記録(北中米カリブ)です。
アメリカの五輪委員会はモスクワに向けて代表選考会を行わなかったのであくまで推測ですが、もし行われていれば氏も選出されていたと思います。
81年ボストンで同走した後「彼は世界No.1」だと評しています。
長くなりました・・・
続きは次回に致します。
いつもながら稚拙な構成の乱文をお読みいただきありがとうございます。
それでは次回も瀬古さんについて、マラソンについて語ります。


 ■現在の写真です。
■現在の写真です。